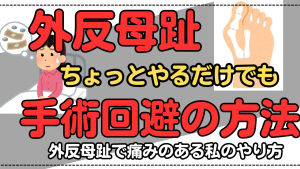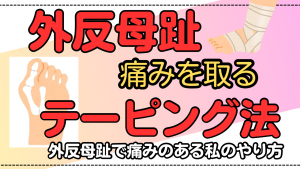足首締めには甲を上げる「甲上げエクササイズ」!
耐震マットのひらめき
ああ、自分のこの足にアーチがあれば痛くならないのに。(偏平足、回内、O脚、開帳足、外反母趾)
ヒールのある靴も、もっと履いてみようかと思うかもしれないのに。
ハイヒールなんてもう無理なのかな。(5cm以上)
足指は傷だらけになるし、肩こりにもなるし、頭も痛くなっちゃうし。
足の力も弱ってるんだろうなあ。今から足を鍛えて履けるようになるまで待つ?あきらめる?
そもそも足が前にすべるから足指が痛くなるのよね。だから外反母趾にもなったんだ。
前にすべらなきゃいいのに。すべらなきゃ・・・
すべるのを止められたら足先は痛くならないんじゃないの?
アーチを作ってやればいいんじゃないの?(2枚張りで可能)
そんなこんなで目の前にあった「耐震マット」にひらめいた瞬間でした。
これなら止まる!すべらない!
そもそもハイヒールを履くためには
「つかむ」という足裏の感覚が必要なのではないか?
と思ったのです。(誰も言ってませんが)
そうでないと前にすべってしまいます。
靴文化の長い、欧米の有名靴メーカーでは土踏まずにあたるところに「シャンク(チャンク)」というものを入れ、工夫しています。(⇒サルヴァトーレ・フェラガモの靴はどのように作られている?)
本来どうやって履くのが本当なのでしょう?
つま先立ちになって歩き続けるのですか?
そんなはずはない。
だから
いつもつま先立ちになっているバレエダンサーの足の使い方に着目したのです。
甲を美しく出して「つかむ」ように鍛錬しているのが、バレエダンサーたちです。(⇒バレエの世界と足裏とハイヒール)
そして
足の甲を上げる時にいちばん足裏のアーチができあがるのです。(⇒動画からわかる足ゆびの曲げ方を解明!ウィンドラスメカニズムについて)
甲上げエクササイズ
最大限に足の甲を上げる練習です。足裏の筋肉につながるので、足首が引き締まります。
(ただし今まで捻挫が多く、足首がグラグラの人にはおすすめできません。その方たちは逆のつま先を上げる練習をおすすめします。)
全指を起こして足趾の腹を床に付けてやっても同じです。(この方がウインドラスメカニズムの形になります)
拇趾の付け根に痛みがある方などは無理はしないように(痛みの感じないやり方はあります)
この形をポアントと言いますが、バレエダンサーはこのように美しく甲を出す動きでは、かかとと前足部で「つかむ」動作をしているのです。アキレス腱を縮めながら伸ばしている状態を作っているのです。
おや?これは私の「縮め伸ばし」の法則と合致しますね。(⇒からだを引き締めるなら「縮め伸ばし」の法則を使う)
本来ヒトが持ち合わせている、その筋力から「バレエ」という美しい舞踏が築き上げられたのでしょうし、この筋力があれば、ヒールのある靴でもしっかり「つかむ」ことができる。
なので、バレエを正しく教えられた方たちは、いくつになってもヒールをうまく履かれているなあというのが実感としてあります。
足裏の筋力があります。
しかし、教えられなかった者にとっては残念すぎるじゃないですか。
研究していくうちにこの「甲を上げる」という動作が
体形を変えることにもつながっていくことがわかったのです。
「甲上げエクササイズ」
「先生、あれすごいわ!」
「踏ん張れるようになった!」
「膝の痛みが消える!」
「ちゃんと立てる!
「脚がまっすぐになる!」
「パフォーマンスが上がる!」
(実は落ちてきている内臓も上がる!膣の訓練に骨盤底筋運動よりわかりやすい!)
O脚やX脚を治すのにも必要です。腹筋を意識するのにも必要です。姿勢を正しくするのにも必要だったのです。
二本の足で、何もつかまずに「立つ」とはどういうことなのか。
前かがみでもなく、お腹を突き出して後ろ重心になるのでもなく、バランスよく「立つ」。
それができなくなってくる高齢者に足りない筋力は、その体の形に表れてくるのです。
思い浮かぶ体の形があるとしたら、ここはいさぎよく、自分の形もチェックしましょうか。
なぜ今回「甲上げエクササイズ」について書いたかというと・・・
「痔」持ちの方からの喜びの声からです。
「トイレであまり踏ん張らないように」と病院で言われるうちに、どうしても「便秘」になってしまうのだそうです。
「便秘」が大敵なのに「便秘」になってしまうという悪循環。それが・・・
トイレで出せるかなあ?の瞬間に「甲上げエクササイズ」をやるだけで「するっと」出るようになったのだそうです。
だから書いてくれと。
嬉しいご報告です。トイレに不安がなくなっただけでも心が軽いと。
膣に関してはちょっと驚きでした。ですが筋肉をたどれば納得なのです。
「つかむ」感覚であって、指を丸めて「にぎる」のではない。
「甲上げエクササイズ」は簡単ですが、コツがあります。やっているうちに他の筋肉を動かすことになるということが実感できる、私独自のものですが、なかなかいいですよ。
さあ、体形・体型を変えていきませんか?
この先にあるあなたの未来のために!
名前:高田祐希
女性専用治療院:二子玉川「きこうカイロ施術院」院長。
・カイロプラクター
・医学気功師
・スポーツトレーナー
・姿勢指導士
・テーピング治療
・耐震マットでハイヒールの考案者
・オーラチャクラセルフリーディング及び宿命鑑定
「体形・体型改善」をすることが「痛み」をなくすことにもつながることを自己の経験をもとに伝授している。ストレッチ、筋トレ、HIPHOP、ダンス、ヨガ、気功などをトレーニングの中で用い、各人に最適で効果のある楽しい運動を提供している。
▼著書「どこに行っても治らなかったひざ痛を10日で治す私の方法」▼
⇒ こちら amazonにとびます
きこうカイロ施術院では、コロナ対策として、フェイスシールド、マスク、手袋、換気などで万全な対策をとって営業しております。体のことで気になるところがあれば、是非一度ご来院ください。
▼きこうカイロ施術院公式サイト▼ 治療料金、初診時の内容などはこちらから
⇒ こちら
▼HOTPEPPERでのご予約は▼ ⇒ こちら
▼YOUTUBE▼ ⇒ こちら
▼アメーバブログ▼ ⇒ こちら
▼公式サイト▼ ⇒ こちら
▼Twitter▼ ⇒ こちら
▼Instagram▼ ⇒ こちら
▼pinterest▼ ⇒ こちら
最後までお読みいただきありがとうございました。
当サイトがあなたのお役にたちますように。
体形改善、体型改善、脚痩せ、お腹痩せ、O脚、X脚、ひざ過伸展、反張膝、ひざ痛、腰痛、肩の痛み、首の痛み、足の痛みでお悩みならば是非一度ご相談ください。
西洋医学・東洋医学(中医学)、両方の立場からあなたのからだをサポートします。
ダイエット、ハイヒールの履き方、歩行、不妊、尿もれ、頻尿などのご相談も同時に受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。