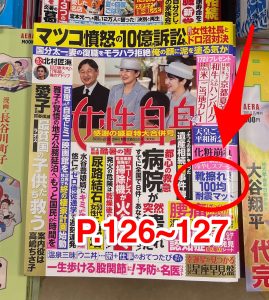東洋医学とは?3つのポイント。
痛みが続く慢性疼痛などの場合なかなか治らないと精神的に参ってしまいますよね。もっと違う考え方で痛みをとらえてみたら
どうでしょう。ということで、今では西洋医学の中にもどんどん取り入れられだした中医学(東洋医学)についてのポイントです。
病院に行って漢方を処方されることも珍しくなくなりました。西洋医学界も変化してきています。東洋医学(中医学)の独特の人体への解釈が、有効なものであることが認識されてきました。
中医学は2千年以上前に中国大陸で考え出された理論ですが、日本に入ってきてから独自に進化、発展してきたのが「東洋医学」「日本漢方」と呼ばれるものです。⇒東洋医学と中医学の違い
わかりだすとはまってしまう面白い哲学のかたまり。⇒全てのものは気でできている
四柱推命や風水ももとをただせば陰陽五行の中医学の考えから派生してきてできているのですから。
では中医学(東洋医学)はどんなふうに考えているのか。ポイントは3つです。この3つの考え方さえわかっておけば自分の不調のサインも見えてくるのではないでしょうか。
東洋医学のからだの考え方、ポイント①
「人間そのものも自然界の一部。だから人体構造も自然界と同じ。」
暖かい空気は上昇し、冷えた空気は下に溜まります。だから人体も頭部がのぼせたり、下半身が冷えたりするのです。
自然界にも季節があるように人間の体調も変化するのです。
自然界にあるものはすべて連動しているので互いに作用や影響しあうのですね。
これは陰陽論、五行学説とも深く関わる考え方です。
東洋医学のからだの考え方、ポイント②
「人体は気、血、水という三つの物質が循環することによって生命を維持している。」
主要な構成要素は「気」「血」「水(津)」。
「気」は経絡をめぐって身体の中をたえず循環し、人間の生命活動を支えるエネルギーのようなもの。
「血」はけつと読みます。血液のことだけでなく、栄養全体を表し、「気」とともにからだ中をめぐって栄養を送ります。
「水(津液)」は血液以外のリンパ液や涙、汗、粘液、尿などの水分のことでからだの中をうるおす働きがあります。
東洋医学のからだの考え方、ポイント③
「人体は 肝・心・脾などの「臓」、胆・小腸・胃などの「腑」 を中心に、からだ全体を連結している経絡から成り立つ。」
肝ー胆
心ー小腸
脾ー胃
肺ー大腸
腎ー膀胱
*三焦は六腑に入りますが腑ではなく臓腑が収まっている胸腔から腹腔にかけてのことをいいます。実体は定かではありません。
*くわしくいうともうひとつ「心包」という臓があります。
腑は臓と対になって臓の働きを補佐する役割をになっているので臓か腑のどちらかに障害が起きると対となる器官にも不調が生じます。
「気」が足りなかったり、停滞したり、逆流したり
「血」が不足したり、障害が起きたり、出血が続いたり
「水」が不足したり、たまりすぎたり、たまったり
バランスが悪くなるのですから、それぞれに特有の症状が出るわけです。
東洋医学(中医学)を語るうえで外せない3つのポイントです。
ご予約はこちら
ご予約、お問い合わせはお電話、下記メールアドレスにて承っております。初来院される方は必ず初診を受けていただきます。
営業時間:10:00~19:00(受付は17:30まで)
定休日:火曜日